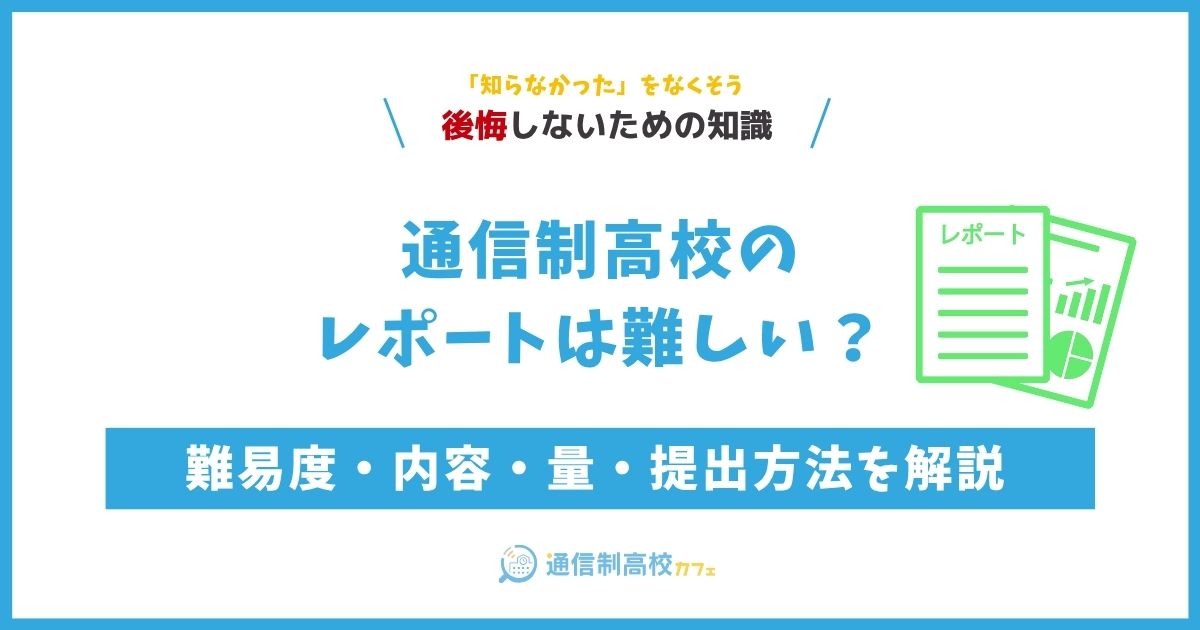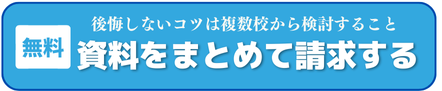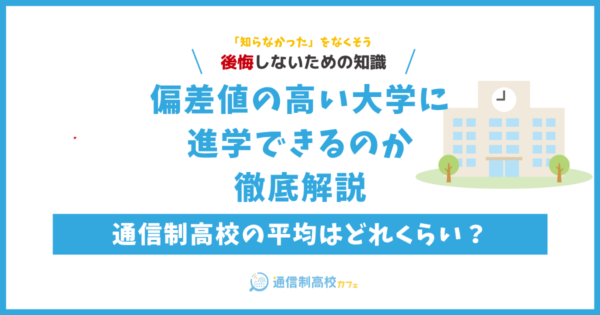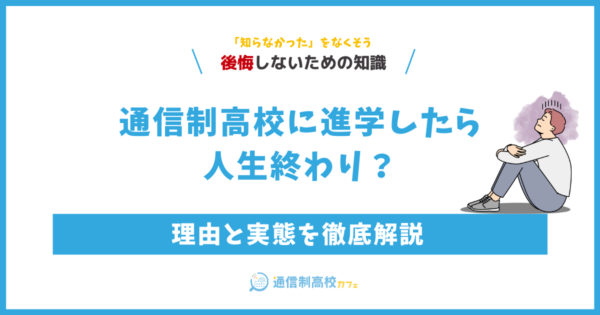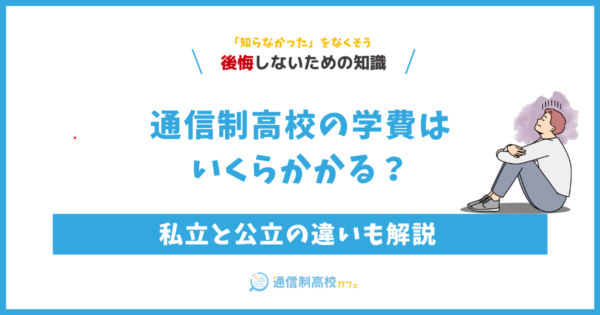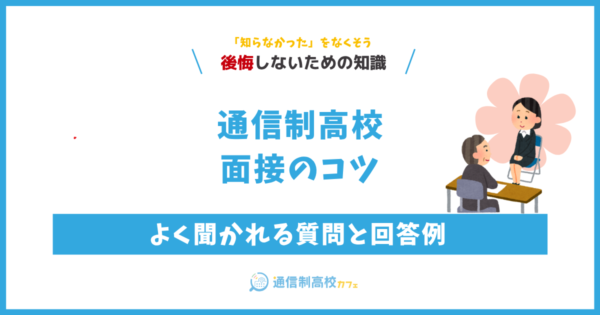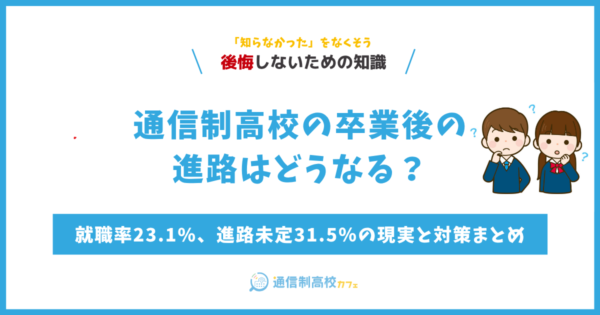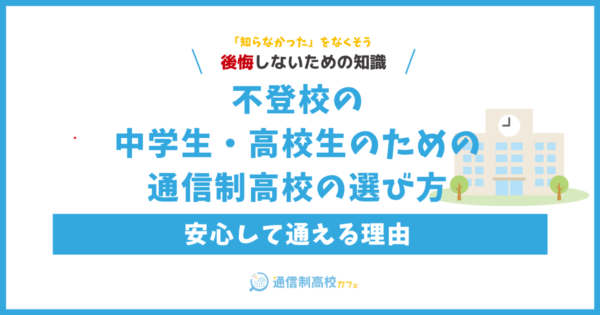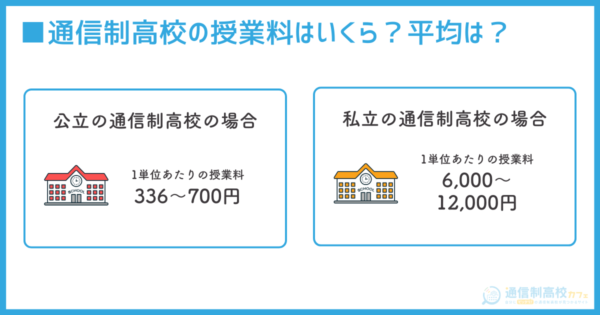- 通信制高校のレポートって何を書くの?
- 通信制高校のレポートの頻度はどれくらい?
- 通信制高校のレポートの提出方法がわからない
通信制高校の学習に欠かせないレポートは、初めての人にとって戸惑うことが多いですよね。
通信制高校のレポートは、教科ごとに課題があり、教科書を参照しながら解く形式で提出頻度や方法も学校によって異なるのが特徴です。
- 通信制高校のレポートとは?
- 通信制高校のレポートの提出頻度・量は?
- 通信制高校レポートの提出方法と流れ
- 通信制高校のレポートは難しい?
- レポートを効率よく進める5つのコツ
- レポートが未提出・不合格だったら?
この記事では、通信制高校のレポートについて、6つの視点から徹底解説します。
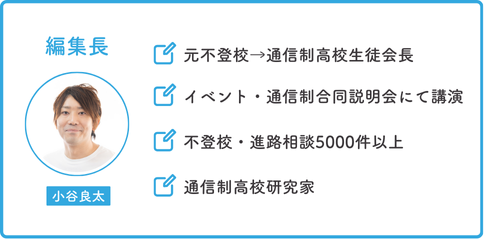
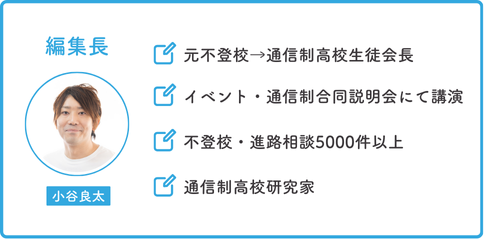
失敗しない通信制高校選びのコツ
自分に合った学校を選びやすい通信制高校ですが、残念ながら、「入学したけど、やっぱり合わなかった…」というケースが少なくないのが現状です。
よくある原因として、
- 1つの学校しか検討しなかった
- 親の意向で決めてしまった
- 学校見学にも行かなかった
といったことが原因としてあげられます。
こういった後悔の声に共通しているのは、十分な比較検討をしなかったということです。この失敗を避けるには、複数の通信制高校を比較し、自分に合った学校を慎重に選ぶことが大切です。


そんな時に役立つのが、通信制高校の一括資料請求サービスです。住所を入力するだけで、通学圏内の学校のパンフレットを簡単に取り寄せられます。
各校の特徴や違いを把握しやすくなり、自分に合った学校を見つけやすくなりますよ。パンフレットは視覚的にも検討しやすく、「この学校は違うな」見極めがしやすくなります。
まだ学校選びに迷っている方は、こうした資料請求サービスを活用してくださいね。
\ 最高に合った通信制高校を見つけよう /
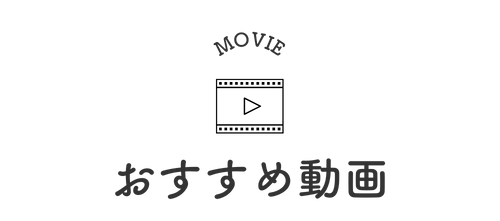
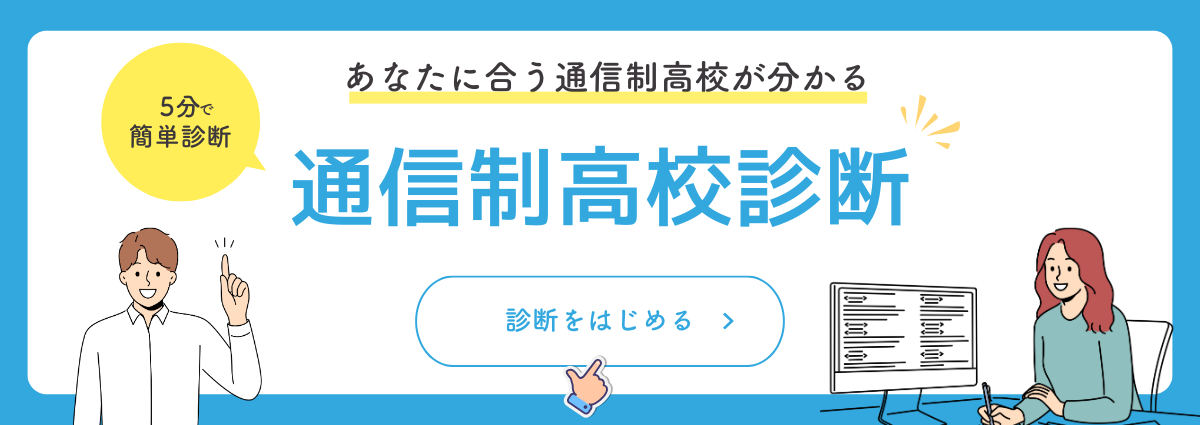
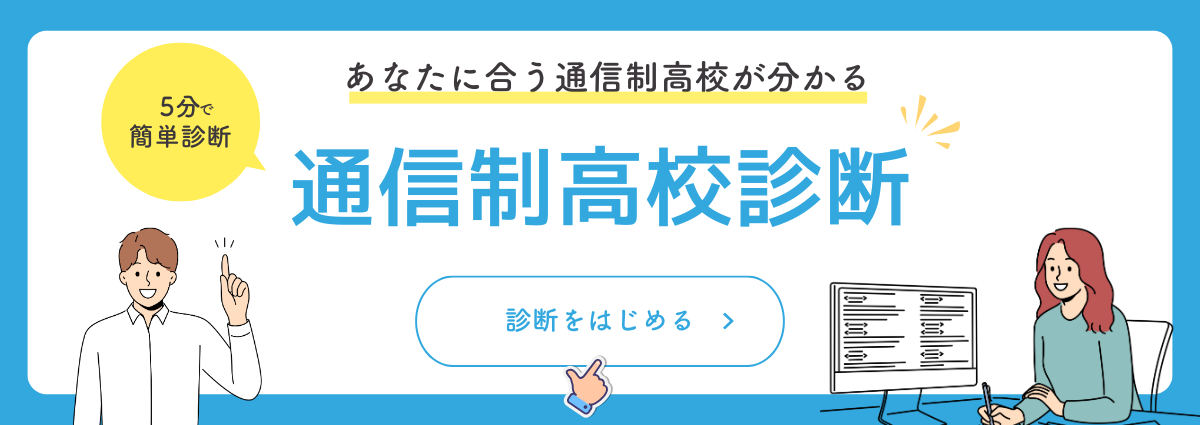


失敗しない通信制高校選びで大事なことは複数の通信制高校から検討することです。その最初のステップが資料請求です。
でも自分の地域から通える通信制高校を探すのは大変だし、1校1校入力フォームに資料請求していくのも大変です。更に資料請求しても音沙汰も無いことも…。



そんな情報収集に便利な一括資料請求サービスの利用がおすすめです。



無料で安心して利用できる以下のサービスを利用して効率的に情報収集していきましょう。
おすすめの資料請求手順
更に以下の「都道府県別!通信制高校・サポート校リンク」を利用して個別に資料請求すればあなたの地域から通える通信制高校の資料すべてを集めることができます! ➞ 全国から通える通信制高校(姉妹サイト)
通信制高校のレポートとは?内容・目的・進め方を解説
通信制高校に入学すると、まず「レポートって何?」と戸惑う人が多いです。
この見出しでは、レポートとはどんな課題なのか、どんな内容なのか、なぜ必要なのかをわかりやすく解説します。
レポートとはどんな課題?授業の代わりになる仕組み
通信制高校における「レポート」は、一般の高校でいうところの授業や宿題にあたる課題です。
通信制では毎日の授業がない分、自宅学習で進める「レポート提出」が単位修得の条件になっています。
文部科学省が定める基準では、通信制高校では次の3つが単位取得に必要とされています。
- レポート提出
- スクーリング(対面授業や登校日)
- 単位認定試験
この中でもレポートは学習の基本となるもので、教科ごとに設定された課題をこなして提出します。
各学校の教育課程に沿って用意されており、提出が完了しなければ単位を取得することはできません。
レポートの主な内容|教科書準拠・問題形式が中心
通信制高校のレポートは、基本的に教科書を見ながら取り組める形式で構成されています。多くの学校では、選択式の問題や穴埋め、語句記入、そして短い記述式問題が中心となっています。国語や英語、倫理など一部の教科では、作文や感想文といった形式が用いられることもあります。
レポートの難易度はそれほど高くなく、中学レベルの復習からスタートするものが多いのが特徴です。基礎的な内容を丁寧に扱っており、教科書の特定ページや章を参照しながら答えを導く形式が多く、自宅での学習がしやすい構成になっています。
また、学年が進むにつれて科目によって内容が少しずつレベルアップしていきますが、決して解けないようなものではありません。基本的には、教科書をしっかり読み込み、内容を理解すれば誰でも解答できるよう工夫されています。
このように、通信制高校のレポートは単位を取得するために欠かせない学習の一環でありつつ、学びやすさにも配慮された設計になっています。勉強が苦手な人でも、段階的に取り組めるよう配慮されているため、安心してチャレンジできる仕組みです。
レポートの目的|単位取得・理解度チェック・自主学習の促進
通信制高校におけるレポートの目的は、単なる課題提出だけではありません。
主に次の3つの目的があります。
- 単位取得のための必須条件
- 生徒の理解度を確認するため
- 自主的に学ぶ力を育てる
1つ目の単位取得のための必須条件ですが、レポートの提出は単位を取るための法的条件のひとつです。
レポートを提出していない場合、そもそも単位認定試験を受けることができません。試験に進むためには、まずレポートの提出を完了させることが必須条件となっています。
2つ目は生徒の理解度を確認するためです。教員はレポートを添削することで生徒の理解度やつまずきやすいポイントを把握します。
通信制では日常的に顔を合わせないため、教員にとっては、レポートが生徒の学習状況を知る唯一の手がかりとなることもあります。
3つ目の自主的に学ぶ力を育てるということですが、決まった授業が少ない通信制では自分で進める力が重要です。
レポートを通じて、自ら学習計画を立てる習慣や、わからないことを調べる力が身につくようになります。



通信制高校のレポートは「ただの宿題」ではなく、単位取得に必須な課題であり、学習の柱です。
自主学習を身につけるための大切な仕組みでもあります。
このQ&Aで解決できなかった場合
今回のQ&Aについて「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。
ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。
いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。
※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。
※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。
通信制高校のレポートの提出頻度・量は?実際のスケジュールを紹介
通信制高校に通い始めたばかりの人や、これから進学を考えている方にとって、「レポートはどのくらいの頻度で出すのか」「1年間で何枚くらい提出するのか」は、多くの人が気になるポイントです。ここでは、実際の提出ペースや教科ごとの量、計画的に進めるためのポイントについて詳しく紹介します。
レポートの提出回数はどれくらい?
通信制高校では、文部科学省の指導要領により「1単位あたり1~3回程度のレポート提出」が標準的とされています。(引用元:文部科学省「高等学校通信教育の現状について P1」)たとえば、年間で25単位を履修する場合は、25単位 × 3回で 約75回のレポートが必要になります 。
75回を年間12か月で割ると、月間約6回の提出となり、これは学校や学習スタイルによって異なるものの、一般的に年間7~10回程度の提出回数が目安となります。
生徒が履修している科目の数にもよりますが、主要教科だけでなく選択科目や実技系教科を含めると、年間で40〜70枚ほどのレポートを提出する必要があります。これは一度にまとめて取り組むにはやや負担が大きく、計画的な進行が求められる分量といえます。
学年や科目ごとのレポート量の目安
通信制高校のレポートは、教科書を読み込みながら自学自習で作成される形式が基本です。(引用元:文部科学省「通信制高等学校の質の確保・向上に関する調査研究協力者会議(第6回)議事録」)これは通信制高校の学びの柱であり、学習内容の定着と理解度確認を目的としています。
また、レポートは教科書の例題や練習問題を中心に構成されており、(引用元:文部科学省(2009年)高等学校学習指導要領解説 総則編 P2 )中学校レベルの復習を含む基礎内容から始まるケースが多いとされています。学習に慣れることを優先し、基本をしっかり固めることが目的となるためです。最初は教科書に基づく一問一答や穴埋め形式の基礎的な課題から始まり、段階を追うごとに「自分なりの問い」を考察するなど、記述の難易度が徐々に高まっていく傾向があります。これは文部科学省の調査研究でも示されており、12通目のレポートでは生徒が自ら問いを立てて考察を深める設計がされている学校もあります 。(引用元:文部科学省「通信制高等学校の質の確保・向上に関する調査研究協力者会議(第6回)議事録」)
通信制高校では、教科ごとに単位取得のためのレポート提出回数(添削指導)とスクーリング(面接指導)時間が文部科学省によって基準設定されています。
たとえば、国語・数学などの主要教科では1単位につきレポート提出3回+1単位時間のスクーリングが目安です。理科や芸術では同じ提出数ながら、実験や実習が多いため面接指導時間が長くなるのが特徴です。また、体育ではレポート提出1回のみでスクーリング時間は多めに設定されています。家庭科や情報などは提出回数・面接時間ともに2~3回・2~8単位時間と幅があります(以下詳細表参照)。(引用元:文部科学省「高等学校通信教育の現状について P1」、「高等学校通信教育の質の確保・向上のためのガイドライン P3」)
このように、科目の特性に応じて、レポートの量は自然と変化していきます。
| 教科カテゴリ | レポート提出回数(添削指導) | スクーリング時間(面接指導) |
|---|---|---|
| 国語・地理歴史・公民・数学・外国語・芸術 | 3回 | 1単位時間 外国語・芸術は4単位時間 |
| 理科 | 3回 | 4単位時間 |
| 保健体育(保健) | 3回 | 1単位時間 |
| 保健体育(体育) | 1回 | 5単位時間 |
| 家庭科・情報・専門教科 | 2〜3回(学校裁量) | 2〜8単位時間(学校裁量) |
(引用元:文部科学省「高等学校通信教育の現状について P1」)
提出スケジュールの管理が重要
通信制高校では単位の認定に必要な条件として、レポートの提出やスクーリング、試験の受験が定められています。
その中でも、レポートを決められた期限までにきちんと出すことは、学習の基本であり、単位取得の前提です。
そのため、提出期限を守ってコツコツ取り組むことが、通信制高校で学ぶうえで最も大切だとされています。
レポートを計画的にこなすことが、レポート提出は単位取得の条件であるだけでなく、自分で計画的に学ぶ力を身につけるうえでも欠かせません。毎日の授業がないぶん、誰も代わりにスケジュール管理をしてくれません。自分で学習の進度を管理する力が必要になります。
学校によっては、あらかじめ年間の提出カレンダーが配布され、どの教科のレポートをいつまでに出す必要があるかが明示されています。春には新しいレポート課題が配布され、夏休みや冬休み中も自宅学習が中心になります。秋から冬にかけては、スクーリングや試験とも重なるため、レポートの提出ラッシュになるケースもあります。
提出期限を過ぎてしまうと、再提出や単位未認定の対象となることもあるため、締切は必ず守る必要があります。スマートフォンのカレンダー機能や、手帳を活用するなどして、常に次の締切を把握しておくことが大切です。日々の生活に「レポートの時間」を組み込んでおけば、急に大量の課題に追われて焦ることも少なくなるでしょう。



通信制高校の学習は、自分のペースで取り組める反面、油断すると提出漏れや遅れが起きやすいです。自分のスタイルに合ったスケジュール管理方法を早めに確立しておくことで、レポート提出の負担を減らしやすくなります。
このQ&Aで解決できなかった場合
今回のQ&Aについて「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。
ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。
いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。
※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。
※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。
通信制高校レポートの提出方法と流れ|ネット・郵送・持参の違い
通信制高校では、学習の中心となるレポートの提出方法にもさまざまな選択肢があります。
この見出しでは、学校ごとの違いや代表的な提出方法、そして提出から添削・返却までの一連の流れをわかりやすく解説します。
レポート提出の方法は学校によって異なる
通信制高校では、レポートの提出方法が学校によって異なるため、入学前にしっかり確認しておきましょう。
従来は郵送や手渡しが主流でしたが、現在ではインターネット環境の整備に伴い、ネットレポート提出を導入する学校も増えています。
たとえば、通信制高校の中でも私立の大手校では、学習専用アプリやポータルサイトを通じてレポートを提出できる仕組みを取り入れており、スマホ1台で完結するケースも珍しくありません。以下導入している私立通信制高校のピックアップリストです。
- 中央高等学院(中央国際高等学校サポート校)
- ルネサンス高等学校
- 英風高等学校
- AOIKE高等学校
- N高等学校
- 第一学院高等学校
- おおぞら高等学院
実際、EdTech総研による2024年の調査では、私立通信制高校の約7割がネットレポート提出や学習ログ管理の仕組みを導入しているとされています(引用元:EdTech総研|2024年通信制高校ICT調査 P1 )。
一方、公立の通信制高校では、依然として紙ベースのレポート提出が主流です。郵送や登校日に直接提出する形式が多く、ICTの活用が十分に進んでいない学校も見られます。文部科学省が令和5年度に実施した「学校における教育の情報化の実態調査」においても、ICT端末の整備率や無線LAN環境は全国的に高いものの、学校によって活用の差があることが指摘されています(引用元:文部科学省|教育の情報化に関する調査結果 P5,P7,P31)。
このように、学校によって提出手段やスケジュールの取り扱いに違いがあるため、自分のライフスタイルに合った方法を選ぶことが、無理なく学習を続けるポイントになります。
郵送・持参・ネットそれぞれの特徴
レポート提出の主な方法には、「郵送」「持参(登校時に提出)」「ネットレポート提出」の3種類があります。それぞれにメリットと注意点があるため、特徴を理解しておくとスムーズです。
まず、郵送による提出は自宅から発送できて便利ですが、封筒や切手の用意は必要です。
基本的には、レポートが完成したらその都度提出する方式が一般的です。提出日が郵便事情に左右されることもあるため、余裕をもった発送が重要です。
登校時に持参する形式では、スクーリングの日などに直接レポートを提出します。この方法は確実に届けられる安心感がありますが、登校日が限られている場合は提出のタイミングを逃さないよう注意が必要です。
近年増えているネットレポート提出では、学習システムや専用アプリを通じて、パソコンやスマートフォンからレポートを送信できます。24時間いつでも提出できる利便性があり、紙の用意が不要なのも大きなメリットです。ただし、ネット環境が不安定だったり、操作に慣れていないと、提出に時間がかかることもあります。
このように、どの方法にも長所と短所があるため、自分の生活スタイルやIT環境を考慮して選ぶことが大切です。
提出から添削までの一般的な流れ
レポートを提出したあとは、学校側で内容を確認し、添削・評価が行われます。通信制高校では、この添削指導が対面授業の代わりを果たす役割を担っています。
まず提出されたレポートは、担当の教員によってチェックされます。提出形式に関係なく、内容が不十分だったり空欄が多い場合は「再提出」となることがあります。そのため、提出前にきちんと見直す習慣をつけることが重要です。
添削では、間違いの指摘やコメントが入ることも多く、特に記述問題では一人ひとりの理解度に応じたアドバイスがもらえる場合があります。これが通信制における学習のフィードバックの機会でもあるため、単なる形式的な提出と捉えずに活用しましょう。
添削されたレポートは、紙提出の場合は郵送や登校時に返却され、ネットレポート提出の場合はシステム上で結果が閲覧できる仕組みになっています。提出後の確認も忘れずに行い、必要があれば復習や追加学習に取り組むことが、理解を深めるうえで効果的です。



提出方法によって利便性や注意点が異なりますが、どの手段でも「期限を守る」ことが最優先です。
また、提出後の添削内容にもきちんと目を通すことで、学習効果がさらに高まります。
このQ&Aで解決できなかった場合
今回のQ&Aについて「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。
ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。
いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。
※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。
※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。
通信制高校のレポートは難しい?つまずきやすいポイントと対処法
通信制高校のレポートは、自分のペースで取り組める一方で、難しいと感じる生徒も少なくありません。
この見出しでは、どんなときに「難しい」と感じるのか、その理由と対処法、学校が提供している支援について紹介します。
よくある悩みと「難しい」と感じる理由
通信制高校に通う生徒の中には、レポートに対して「何を書けばいいかわからない」、「教科書を読んでも理解できない」と感じる人が多くいます。特に、自学自習に慣れていない場合、初めてのレポートで戸惑うのはごく自然なことです。
レポートの形式は学校や教科によって異なりますが、多くの場合は教科書を読んで答える問題形式となっており、決して高度な内容ではありません。しかし、解説がないまま一人で取り組むため、理解が追いつかないと「難しい」と感じやすくなります。
また、提出期限が迫っているのにやる気が出ない、量が多くて後回しにしてしまう、といった心理的な負担も、レポートが難しく感じる一因です。内容そのものというより、「一人でこなさなければならない」というプレッシャーが影響しているケースが多いのです。
レポートが進まないときの対処法
レポートが手につかないときは、まず「1問だけでも解く」という気持ちで机に向かうことが大切です。最初の一歩を踏み出せば、徐々に集中力が高まり、自然と続けられるようになることもあります。
また、勉強する時間帯を決めて習慣化することも効果的です。毎朝10時に1時間、または夕食後の30分だけ、というように自分に合ったスケジュールを組むことで、心理的なハードルが下がります。
それでも進まないときは、問題の難易度に注目しましょう。全体を見て取りかかりやすい教科や単元から着手することで、達成感を得やすくなります。得意な科目から始めて弾みをつけるのも一つの方法です。
わからない箇所があれば、メモを取りながら進め、後でまとめて質問する準備をしておくと、教員に相談しやすくなります。完全に理解しようとせず、「とりあえず埋めて出す」よりも、「考えた痕跡を残して提出する」ことの方が、評価されることが多いです。
学校のサポート制度を活用しよう
通信制高校の多くは、生徒が一人で悩まないようにさまざまな学習支援制度を設けています。代表的なのは、質問対応のメールサポートや電話相談、スクーリング時の個別指導などです。
私立の通信制高校では、オンライン学習ツールや動画授業が充実しているところもあり、教科ごとのレクチャーを視聴しながらレポートに取り組むことができます。こうしたツールを活用すれば、理解が深まり、「自力で解けた」という実感を得やすくなります。自分で解けたという経験は、学習への意欲や自信につながり、継続的な学習にも前向きに取り組めるようになります。
また、担任の先生や学習コーチによる定期的な面談も、モチベーションを保つうえで大きな助けになります。悩みやつまずきは、自分だけで抱え込まず、早めに相談することが大切です。
特に転入生や不登校経験のある生徒にとって、手厚いフォロー体制は心強い存在となるでしょう。学校によっては、週1回の通学型コースを選べば、対面指導を受けながら安心して学習できる環境も整えられています。



通信制高校のレポートは「内容」より「自分で進める力」が問われる課題です。難しさを感じたときは、すぐに対策をとり、学校のサポート制度を積極的に活用することが成功のカギとなります。
このQ&Aで解決できなかった場合
今回のQ&Aについて「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。
ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。
いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。
※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。
※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。
レポートを効率よく進める5つのコツ|勉強が苦手でもできる工夫
通信制高校のレポートを毎回こなすのは、簡単そうで意外と手間がかかるものです。
特に勉強が苦手な人にとっては、「どこから手をつければいいの?」と悩んでしまうこともあるでしょう。
ここでは、効率よくレポートを進めるための具体的な工夫を5つ紹介します。
教科書を繰り返し活用して理解を深める
通信制高校では、基本的に教科書をもとに学習が進みます。まずは教科書を丁寧に読み、理解しにくい箇所は何度も見直すことが大切です。
レポートの問題は教科書の内容から出題されることが多いため、繰り返し読み込むことで自然と答え方のパターンも身についてきます。
書き込みながら読む、見出しごとに要点をまとめていくなど、教科書を“読むだけ”にせず、能動的に使うことがポイントです。
一気にやらずこまめに進める
レポートをまとめてやろうとすると、量に圧倒されて「やる気が出ない」状態に陥りやすくなります。
そうならないためには、1日に1教科だけ取り組むなど、小さな目標を決めてこまめに進めることがポイントです。
「15分だけやる」「1ページだけやる」といった小さなタスクから始めることで、精神的なハードルが下がります。続けているうちに集中力が高まり、気づけば予定以上に進められていたということもあります。
わからない部分は質問する
レポートで立ち止まってしまう最大の原因は、「わからないところをそのままにしてしまうこと」です。理解できないまま時間が過ぎると、やる気を失いやすくなります。
通信制高校では、メールやチャットで先生に質問できるサポート制度が整っていることが多く、困ったときには積極的に活用しましょう。わからない箇所を日頃からメモしておき、まとめて質問すると効率的に解決できます。
また、スクーリングの機会を利用して直接先生に質問するのも効果的です。教員も、生徒の「学びたい」という姿勢を歓迎してくれることが多く、遠慮する必要はありません。
さらに最近では、ChatGPTのようなAIを使って疑問点を調べる生徒も増えています。すぐに先生に聞けない場合でも、AIに質問することでヒントが得られることがあります。もちろん、最終的には教科書や先生の説明をもとに理解を深めることが大切ですが、AIを補助的に使うことで、つまずきを減らす手助けになるでしょう。
スマホやデジタルツールを活用
今ではスマートフォンやタブレットを使って学習をサポートする便利なアプリやサービスが豊富にあります。
音声で解説してくれるアプリ、動画で学べる教材、AIが問題を解説してくれるツールなど、無料でも質の高いサービスが揃っています。
また、スケジュール管理アプリを活用すれば、レポート提出日や進捗の管理も簡単にできます。通知機能を設定しておけば、うっかり忘れてしまうリスクも減ります。
紙とペンだけに頼らず、デジタルの力を上手に使えば、効率よく楽しく学習を進めることができます。
モチベーション維持の工夫
勉強が苦手な人ほど、レポートを続けるには「やる気を保つ仕組み」が必要です。
たとえば、「レポート1枚終わったら好きなお菓子を食べる」「週末にゲームするために平日は1日1教科頑張る」といったごほうび制度は意外と効果があります。
また、目に見える形で達成感を味わえるように、進捗をカレンダーにチェックしていくのもおすすめです。進んでいる実感がモチベーションにつながります。
さらに、保護者や友人に「今日はここまで終わった」と報告することも、小さな達成感につながり、継続する力になります。「頑張っている自分を褒めてあげる意識」を持つことが、勉強習慣を支える土台になります。



勉強が苦手でも、やり方次第でレポートは進められます。
小さな工夫を積み重ねることが、効率よく続けるコツです。
このQ&Aで解決できなかった場合
今回のQ&Aについて「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。
ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。
いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。
※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。
※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。
レポートが未提出・不合格だったら?単位に影響するのか
通信制高校においてレポートは、単位を取得するために欠かせない学習活動です。
「提出し忘れてしまったら?」「不合格になったらどうなるの?」と不安に思う方も多いでしょう。
この見出しでは、未提出や不合格がどのように単位に影響するのか、具体的に解説します。
レポート未提出が与える影響
通信制高校では、レポートの提出は単位認定の絶対条件の1つに含まれます。
スクーリングの参加や試験の受験と並んで、必ずクリアしなければならない項目です。
レポートを提出しない、あるいは提出数が不足している場合は、その教科の単位が認定されません。
つまり、どれだけスクーリングに出席していても、試験で良い点を取っていても、レポートが未提出であれば単位を落としてしまいます。
単位が足りないと卒業に必要な条件を満たせなくなるため、進級や卒業に大きな影響を及ぼす可能性があります。
このように、レポートは単なる課題ではなく、卒業資格に直結する「必須条件」として扱われています。
再提出・やり直しになるケース
提出済みのレポートであっても、内容が不十分であれば「再提出」や「補足の提出」を求められることがあります。
特に空欄が多い、誤答が多い、考え方がまったく記載されていないといった場合には、合格扱いにはなりません。
再提出が必要な場合、学校から指示が届くか、返却されたレポートにコメントが記載されます。
この際は、ただ直すだけでなく、なぜ間違ったのかを振り返ることが重要です。そうすることで、次のレポートや試験にも役立ちます。
また、科目によっては提出できる回数に制限がある場合もあります。
何度も提出し直すことになると、ほかの科目の学習に影響が出るため、できるだけ1回で合格を目指すのが理想です。
締切を守るために必要なこと
レポート提出の締切を守るためには、まず年間スケジュールや提出カレンダーを把握しておくことが大切です。
特に公立の通信制高校では、提出日が毎月決まっている場合が多く、1日でも遅れると受理されないことがあります。
提出形式が郵送の場合は、消印有効なのか必着なのかを確認しておくと安心です。
提出日ギリギリの投函では、郵便事情によって間に合わない可能性もあるため、常に余裕をもって取り組むことを心がけましょう。
また、スケジュール管理が苦手な人は、スマートフォンのリマインダー機能や、カレンダーアプリを活用するのがおすすめです。
レポート1枚ごとの提出予定を設定し、通知を受け取ることで、うっかり忘れを防ぐことができます。
繰り返しになりますが、レポート未提出=単位取得不可という厳しいルールがある以上、日々の学習計画にレポート作成の時間をしっかり組み込むことが重要です。



レポートは「出せばOK」ではなく「内容も評価対象」です。
締切を守り、質も保つことが単位取得のカギです。
このQ&Aで解決できなかった場合
今回のQ&Aについて「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。
ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。
いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。
※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。
※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。
後悔しない通信制高校の選び方│プロ直伝
自分に合った学校を選びやすい通信制高校ですが、残念ながら、「入学したけど、やっぱり合わなかった…」というケースが少なくないのが現状です。
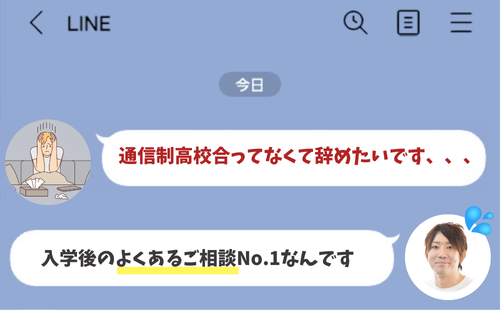
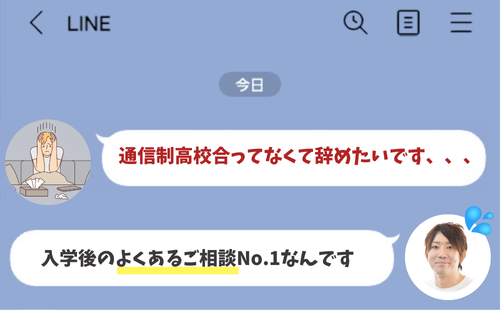
よくある原因として、
- 1つの学校しか検討しなかった
- 親の意向で決めてしまった
- 学校見学にも行かなかった
といったことが原因としてあげられます。
こういった後悔の声に共通しているのは、十分な比較検討をしなかったということです。この失敗を避けるには、複数の通信制高校を比較し、自分に合った学校を慎重に選ぶことが大切です。
そんな時に役立つのが、通信制高校の一括資料請求サービスです。住所を入力するだけで、通学圏内の学校のパンフレットを簡単に取り寄せられます。
各校の特徴や違いを把握しやすくなり、自分に合った学校を見つけやすくなりますよ。パンフレットは視覚的にも検討しやすく、「この学校は違うな」という見極めもしやすくなります。
まだ学校選びに迷っている方は、こうした資料請求サービスを活用してくださいね。
まずは多くの学校から検討していくことが大事なのですが、その話の進め方によっては、学習意欲の低下や中退につながってしまうケースもあります。
特に不登校経験がある場合は、本人の心の準備が整っているかどうかをしっかりと見極めることが大切です。進路の話を急かすのではなく、まずは日常的な会話から始めて、少しずつ本人の気持ちに寄り添っていきましょう。
もし進路の話ができないときは、当サイト管理人が運営する無料講座を受けてください。
関連:失敗しない進路の話の進め方3ステップ講座プレゼント中(不登校解決講座)
決して親の期待や周囲の意見だけで決めるのではなく、「なぜ通信制高校で学びたいのか」「どんな高校生活を送りたいのか」という本人の思いを丁寧に確認していくことが重要です。学校見学や体験授業にも参加して、実際の雰囲気を感じることで、より具体的なイメージが持てるはずです。
学校選びでは、サポート体制や通学のしやすさ、費用面なども含めて総合的に検討することが必要です。焦らずじっくりと情報を集め、本人と保護者が納得できる選択をすることで、充実した高校生活への第一歩を踏み出すことができるでしょう。
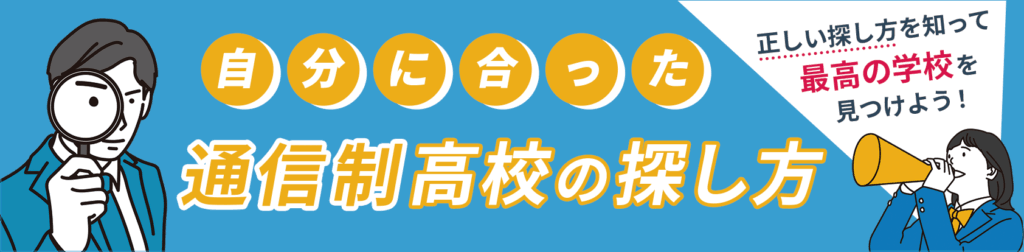
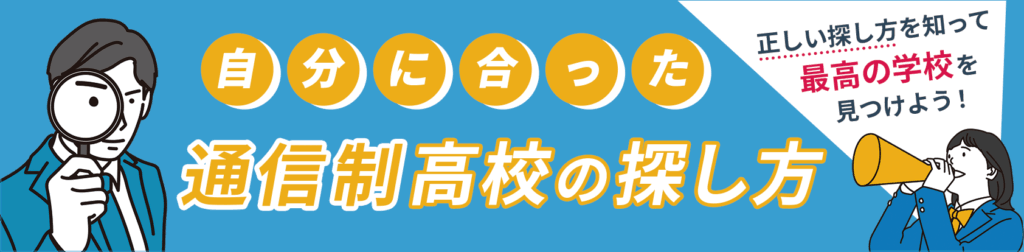
自分に合った通信制高校を探している方へ
通信制高校に入学したい、お子さんを通わせたいと思っても、どんな通信制高校があるのか探して、学校がご自身に合っているのか選ぶのは難しいものですよね。
高卒資格取得はもちろん、スクーリング日数やスクーリング形式、ご自宅からの通学のしやすさ、不登校からの学び直し、大学進学など、入学目的もさまざまですが、一番大切なのはその学校の雰囲気や環境がお子さん自身に合っているかどうかが大事です。
「通信制高校カフェ」では、全国から通える通信制高校やサポート校の情報を豊富に掲載しています。まずは気になる学校を複数ピックアップして、資料請求をしていきましょう。
資料が手元にあると、「この学校はいいな」「この学校は合っていないな」と取捨選択もしやすいですし、お子さんとの情報共有もしやすいです。
また並行して、気になる学校が出てきたらぜひ当サイトの口コミも確認してみましょう。
口コミの正しい活用方法を知ることで、学校選びの貴重な判断材料となります。
例えば口コミで確認した情報を元に、学校見学の時に「先生方のサポート体制について詳しく教えていただけますか?」「オンライン授業の具体的な進め方を教えてください」など、気になった点を質問してみましょう。これだけでも、より具体的な情報が得られますよね。
口コミは「こういう点をチェックしよう」という参考程度に考えて、実際に自分の目で確かめることが大切です。ネットの情報に振り回されるのではなく、その情報を「確認すべきポイント」として活用していくのがおすすめです。
ちなみに、全国展開している通信制高校の場合、キャンパスによって環境が異なることもあります。だからこそ、資料請求し口コミを調べた後は、気になるキャンパスの見学会には必ず参加することをおすすめします。
口コミは「参考程度」として位置づけ、実際の見学や様々な情報源と組み合わせることで、より良い学校選びができるでしょう。


まとめ|通信制高校のレポートはコツを掴めば乗り越えられる
通信制高校のレポートは、単位を取得するために必ず取り組まなければならない大切な学習課題です。スクーリングや試験と並び、卒業に直結する要素であるため、提出を怠ることはできません。特に未提出や再提出になると、単位認定に影響が出るため注意が必要です。
難しそうに見えるレポートでも、教科書や副教材を活用しながら少しずつ進めることで、誰でも取り組める内容になっています。実際、多くの通信制高校では問題形式で構成されており、調べながら答えることも可能です。ポイントは「自分に合った進め方」を見つけることです。
勉強が苦手な人でも、教科書とワークを組み合わせたり、時間を区切って少しずつ取り組んだりすれば、無理なく習慣化できます。疑問点があればすぐに質問する姿勢も大切です。最近ではスマホアプリやオンライン学習ツールの導入が進んでおり、学習環境もよりサポートされやすくなっています。
さらに、通信制高校では先生やスタッフによるサポート体制も整っています。質問対応や個別指導、スクーリングでのフォローなど、一人で抱え込まずに相談できる環境があることを覚えておきましょう。こうした支援をうまく活用することで、レポート学習のハードルはぐっと下がります。
不合格や未提出といったつまずきがあっても、落ち込まずに再チャレンジする姿勢が大切です。提出期限を守るためには、スケジュールをしっかり管理し、こまめに準備を進めておくことが効果的です。焦らずに自分のペースで進めれば、レポートを乗り越えるのは十分可能です。
通信制高校の学びは、やり方次第で大きく変わります。自分に合った工夫と支援を取り入れながら、前向きに取り組んでいきましょう。
このQ&Aで解決できなかった場合
今回のQ&Aについて「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。
ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。
いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。
※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。
※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。
失敗しない通信制高校選びのコツ
自分に合った学校を選びやすい通信制高校ですが、残念ながら、「入学したけど、やっぱり合わなかった…」というケースが少なくないのが現状です。
よくある原因として、
- 1つの学校しか検討しなかった
- 親の意向で決めてしまった
- 学校見学にも行かなかった
といったことが原因としてあげられます。
こういった後悔の声に共通しているのは、十分な比較検討をしなかったということです。この失敗を避けるには、複数の通信制高校を比較し、自分に合った学校を慎重に選ぶことが大切です。


そんな時に役立つのが、通信制高校の一括資料請求サービスです。住所を入力するだけで、通学圏内の学校のパンフレットを簡単に取り寄せられます。
各校の特徴や違いを把握しやすくなり、自分に合った学校を見つけやすくなりますよ。パンフレットは視覚的にも検討しやすく、「この学校は違うな」見極めがしやすくなります。
まだ学校選びに迷っている方は、こうした資料請求サービスを活用してくださいね。
\ 最高に合った通信制高校を見つけよう /
当サイトの学校情報の内容に記載ミスや古い情報又は、新規キャンパスの情報がある場合は、お手数ですが下記の情報提供フォームからご連絡いただけますと幸いです。
>>通信制高校・サポート校情報提供フォームはこちら
この記事で解決できなかった場合
最後までお読みいただきありがとうございました。
今回の記事を読んで「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。
ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。
いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。
※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。
※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。
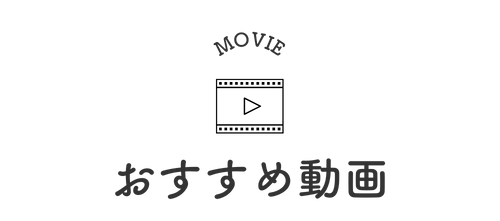
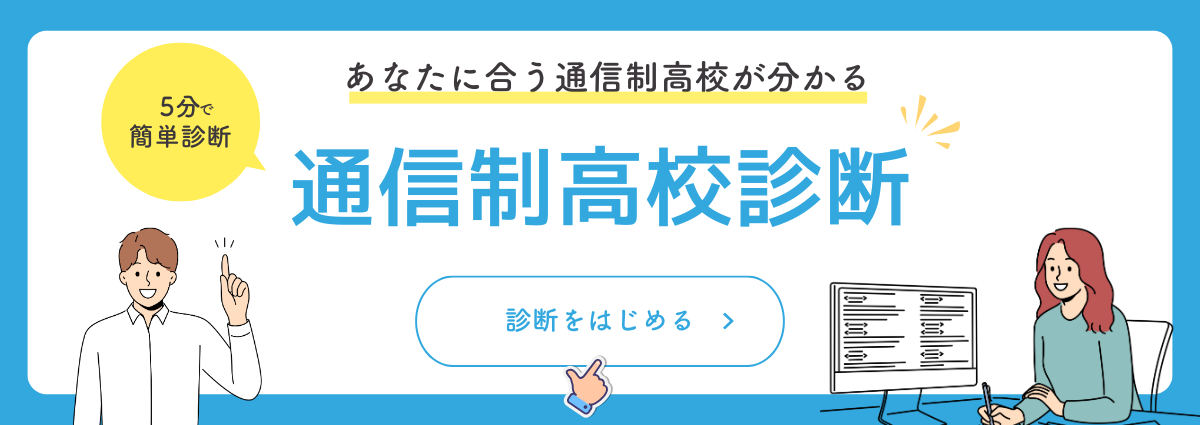
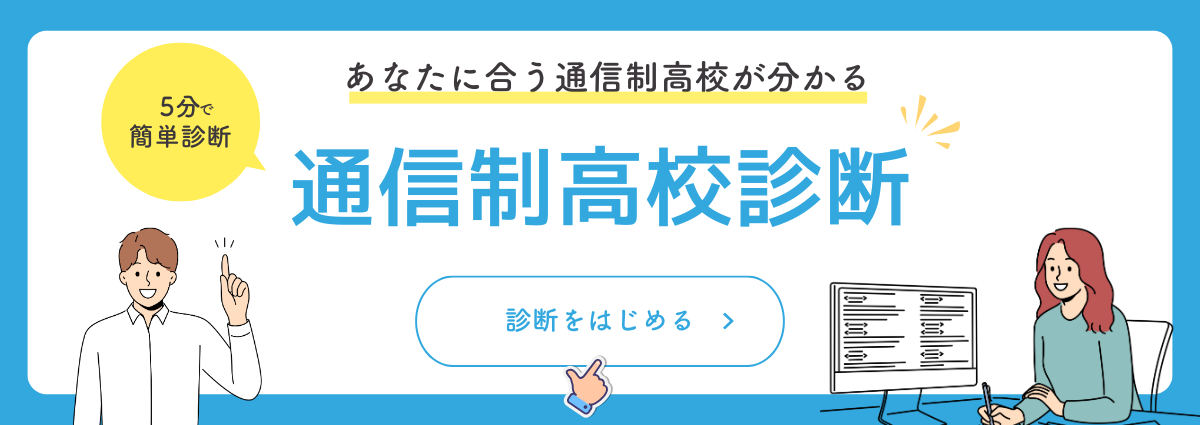


失敗しない通信制高校選びで大事なことは複数の通信制高校から検討することです。その最初のステップが資料請求です。
でも自分の地域から通える通信制高校を探すのは大変だし、1校1校入力フォームに資料請求していくのも大変です。更に資料請求しても音沙汰も無いことも…。



そんな情報収集に便利な一括資料請求サービスの利用がおすすめです。



無料で安心して利用できる以下のサービスを利用して効率的に情報収集していきましょう。
おすすめの資料請求手順
更に以下の「都道府県別!通信制高校・サポート校リンク」を利用して個別に資料請求すればあなたの地域から通える通信制高校の資料すべてを集めることができます! ➞ 全国から通える通信制高校(姉妹サイト)