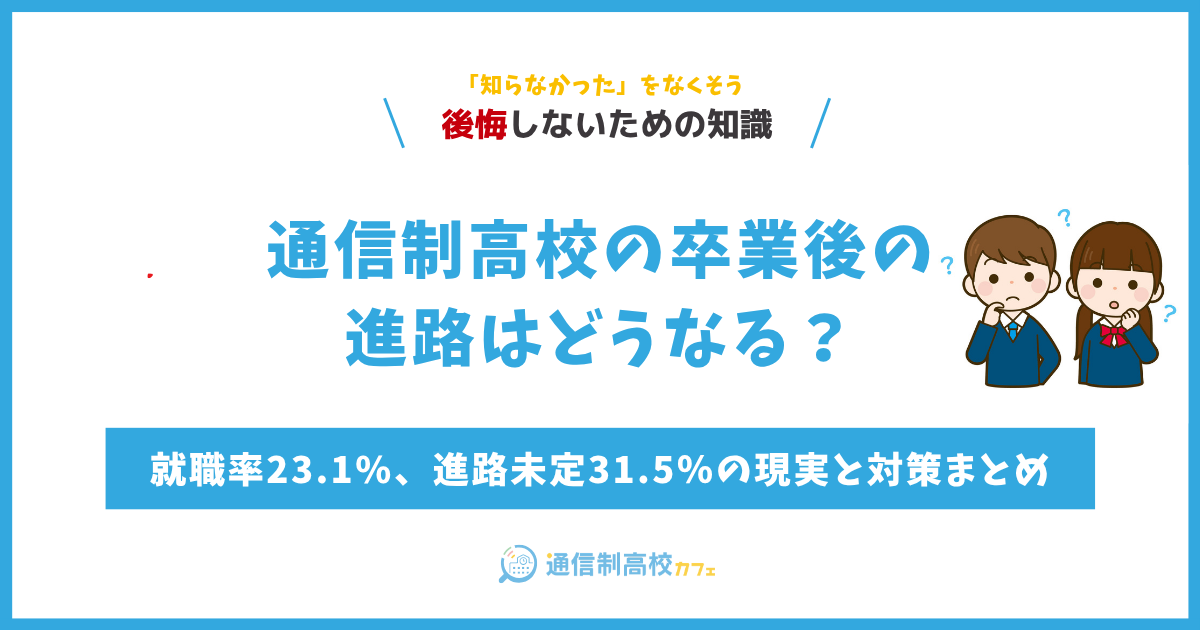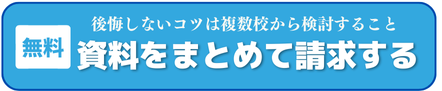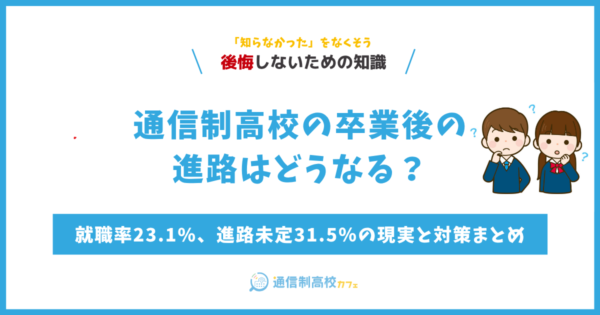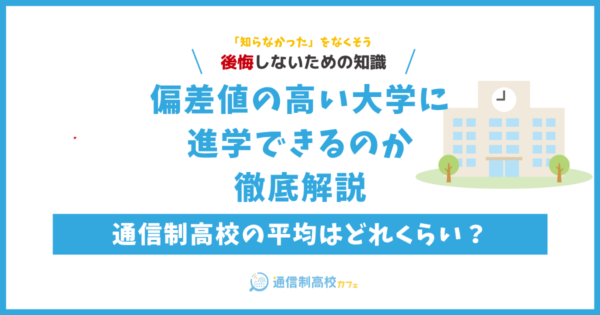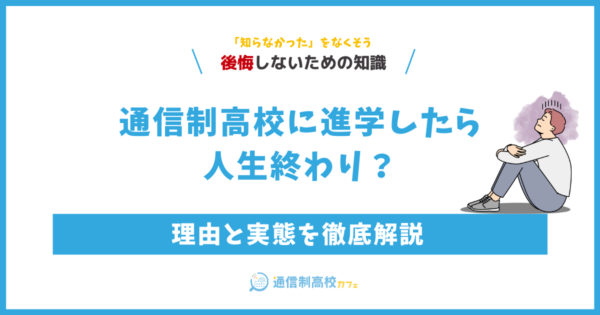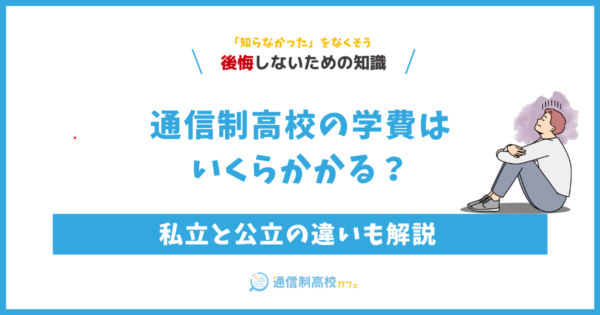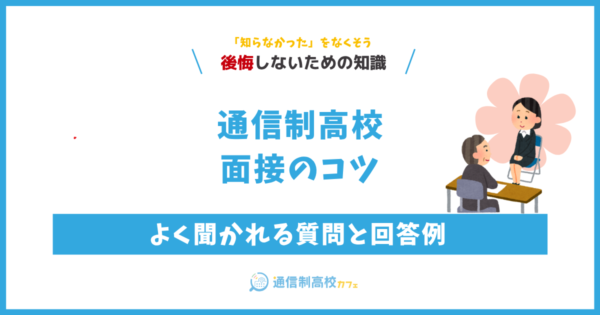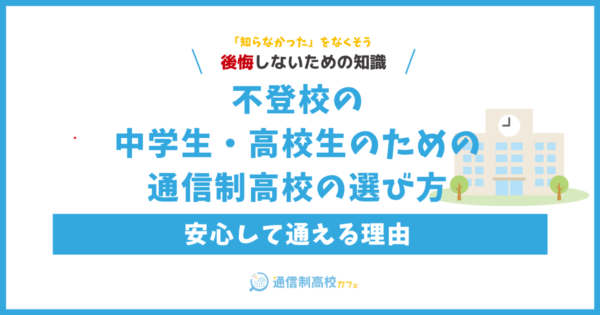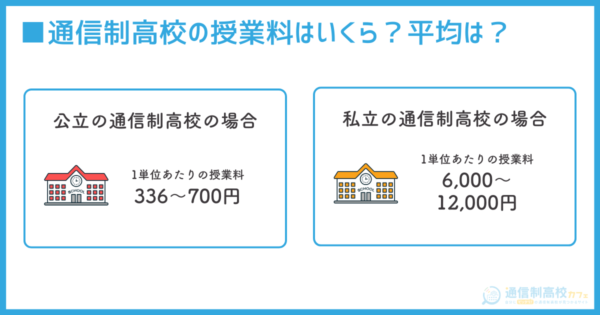- 通信制高校の進路って本当に大丈夫?
- 通信制高校から大学に進学できるの?
- 通信制高校は就職に不利って聞いて不安
通信制高校を選んだあとの進路に不安を感じるのは、決して珍しいことではありません。
というのも、通信制高校は全日制と違って登校日数が少なく、「勉強の質が低いのでは?」「卒業後の選択肢が限られるのでは?」といったイメージを持たれやすいからです。さらに、身近に通信制出身の先輩がいないと、将来の姿を思い描きにくいのも不安につながります。
ですが、結論から言えば、通信制高校からでも大学進学や希望の就職は十分に可能です。
ただし、チャンスを逃さないためには、在学中から意識しておくべき3つの重要な対策があります。
- 学力や進学対策のための「計画的な学習」
- 志望校・志望職に向けた「情報収集と進路相談」
- 面接や履歴書に活かせる「課外活動や資格取得」
といった行動が、通信制高校の進路成功のカギを握ります。
この記事では、通信制高校の進路に関する現実や誤解、進学・就職に向けた具体的な対策について解説します。
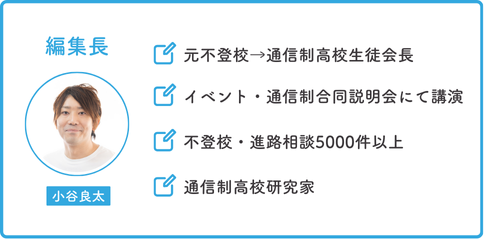
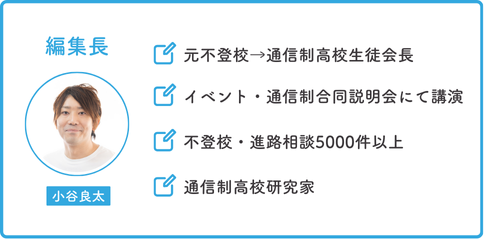
失敗しない通信制高校選びのコツ
自分に合った学校を選びやすい通信制高校ですが、残念ながら、「入学したけど、やっぱり合わなかった…」というケースが少なくないのが現状です。
よくある原因として、
- 1つの学校しか検討しなかった
- 親の意向で決めてしまった
- 学校見学にも行かなかった
といったことが原因としてあげられます。
こういった後悔の声に共通しているのは、十分な比較検討をしなかったということです。この失敗を避けるには、複数の通信制高校を比較し、自分に合った学校を慎重に選ぶことが大切です。


そんな時に役立つのが、通信制高校の一括資料請求サービスです。住所を入力するだけで、通学圏内の学校のパンフレットを簡単に取り寄せられます。
各校の特徴や違いを把握しやすくなり、自分に合った学校を見つけやすくなりますよ。パンフレットは視覚的にも検討しやすく、「この学校は違うな」見極めがしやすくなります。
まだ学校選びに迷っている方は、こうした資料請求サービスを活用してくださいね。
\ 最高に合った通信制高校を見つけよう /
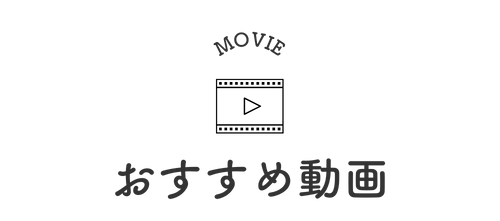
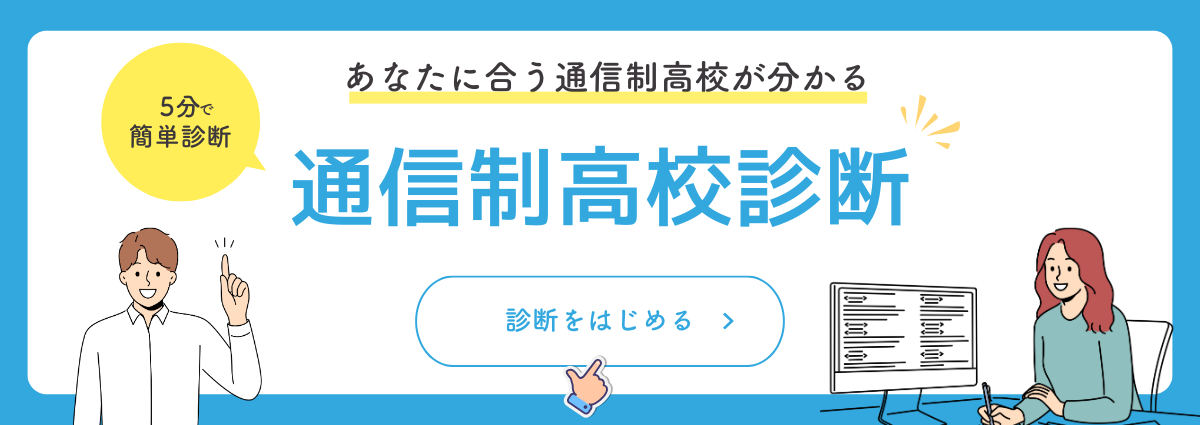
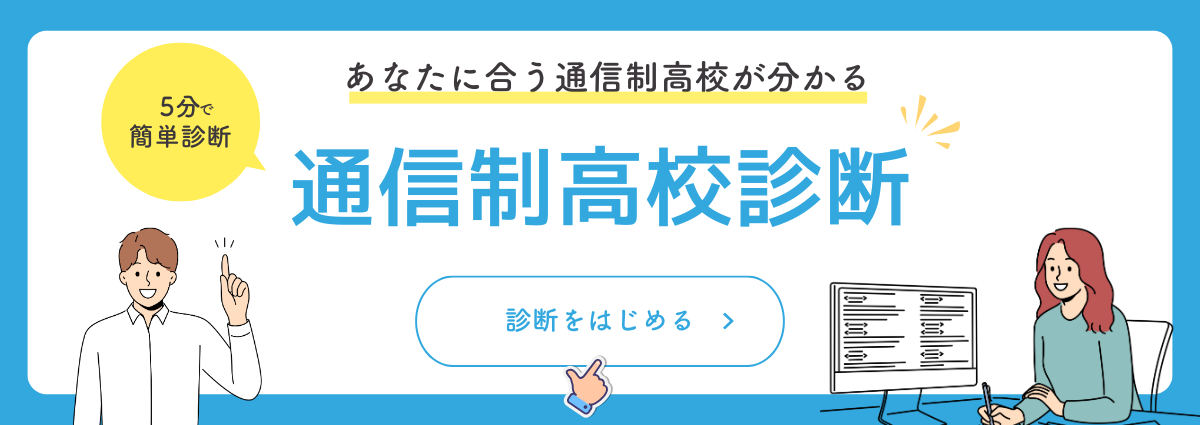


失敗しない通信制高校選びで大事なことは複数の通信制高校から検討することです。その最初のステップが資料請求です。
でも自分の地域から通える通信制高校を探すのは大変だし、1校1校入力フォームに資料請求していくのも大変です。更に資料請求しても音沙汰も無いことも…。



そんな情報収集に便利な一括資料請求サービスの利用がおすすめです。



無料で安心して利用できる以下のサービスを利用して効率的に情報収集していきましょう。
おすすめの資料請求手順
更に以下の「都道府県別!通信制高校・サポート校リンク」を利用して個別に資料請求すればあなたの地域から通える通信制高校の資料すべてを集めることができます! ➞ 全国から通える通信制高校(姉妹サイト)
通信制高校の進路は本当に不利?世間のイメージと現実
通信制高校に対して「進路が不利になるのでは」「卒業しても就職が難しいのではないか」といった不安を抱く人は少なくありません。特に初めて通信制高校を検討する保護者にとっては、進学や就職の実績が気になるところです。けれども、実際の進路状況を正しく理解すれば、必ずしも不利とは言えないことがわかってきます。この章では、よくある誤解と現実の進路実績について整理します。
「通信制高校の進路は悲惨」という声の背景
通信制高校には、世間から「進路がうまくいかない」「まともな就職先がない」というネガティブなイメージがつきまとうことがあります。その背景には、過去に抱かれていた「全日制に行けなかった生徒のための選択肢」という誤解が今も一部で残っていることが影響しています。
また、通信制高校には不登校や中退経験のある生徒が多いという認識も強く、それが「将来が心配」「普通の高校生活が送れない」といった偏見につながっている面もあります。ただ、通信制高校は現在では非常に多様な学び方が可能であり、学業だけでなくスポーツや芸能活動、家庭の事情などさまざまな理由で選ばれています。生徒自身の前向きな選択で通信制を選ぶケースも増えているのです。
「悲惨」という言葉に引きずられてしまうと、正しい判断ができなくなってしまいます。実態はもっと多様で、本人の努力や学校のサポートによって進路は大きく広がっているのが現実です。
実際の進学・就職率のデータから見る現状
実際、文部科学省の「学校基本調査」(平成30年度)によると、通信制高校卒業生のうち大学等に進学する割合が18.0%、専門課程の専修学校進学が21.7%で、合計すると約39.7%にのぼります(出典:文部科学省「学校基本調査」平成30年度)。全日制に比べればやや低い数字ではあるものの、希望すれば進学の道が開かれていることは事実です。
また、通信制高校卒業生の就職率は約23.1%にのぼるとされており、(出典:文部科学省「高等学校通信教育の現状について」) 企業の中には「自分で学習管理ができる人材」として通信制高校出身者を評価するところもあります。進学も就職も、目標を持ち準備をしてきた生徒にとっては十分に実現可能な選択肢です。
一方で、同調査では通信制高校卒業時の進路未定率が31.5%と、およそ3人に1人が進路を決めずに卒業している実態が明らかになっています。(出典:文部科学省「検討を進めるための参考資料」)ただそれも、卒業後すぐに社会へ出るのではなく、自分の時間を確保してから進路を決めたいという考えや、進学準備に時間を使うためであることも多く、「失敗」や「放棄」とは限りません。数字の印象だけで判断せず、その内訳や背景を理解することが大切です。
全日制と通信制の進路における違いとは?
全日制高校と通信制高校では、進路に関する環境やサポートの仕組みに違いがあります。たとえば、全日制では進学指導の担当が定期的に面談を行い、進路希望に合わせて具体的なサポートをしてくれるケースが一般的です。対して通信制では、自主学習の割合が高く、学校によっては進路相談の機会が限られている場合もあります。
ただし、これは通信制高校が進路支援をしていないという意味ではありません。最近では、生徒一人ひとりの目標に合わせた個別の進路サポート体制を整えている学校も増えています。中には、進学専用のカリキュラムや、就職に強いキャリア指導を行う通信制高校も存在します。



つまり、進路に不安があるときは、通信制高校だからという理由で一概に判断するのではなく、「どのような支援体制が整っているか」や「自分の目標に合っているか」をしっかり見極めることが必要です。選ぶ学校と、そこでどのように過ごすかが将来を大きく左右します。
このQ&Aで解決できなかった場合
今回のQ&Aについて「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。
ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。
いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。
※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。
※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。
通信制高校からの進学|大学・専門学校に行ける?
通信制高校に通っていても、進学は十分に可能です。しかし、「本当に大学に行けるの?」「専門学校の受験は難しくない?」といった疑問や不安を抱える人も多いはずです。
この見出しでは、大学や専門学校への進学実績や方法、合格に近づくために必要な準備や工夫について詳しく解説します。
大学進学は本当に可能?合格実績と受験方法
通信制高校から大学に進学することは十分に可能です。実際、文部科学省の調査資料に登場する私立通信制単位制高校(2009年度調査)では、卒業生の約60%が大学や専門学校へ進学しています。(出典:文部科学省「第3章 通信制高校に学ぶ生徒の現状と課題」)指定校推薦や一般受験、AO入試など、選択肢も全日制と同じように幅広く用意されています。
もちろん、全日制高校の進学率が56.5%に対し、通信制高校では17.6%とやや低めの傾向にありますが 、(出典:文部科学省「高等学校通信教育の現状について」)それは環境の違いというよりも、生徒一人ひとりの事情や目標の違いによるものです。努力次第で国公立大学や有名私大に合格している例も少なくありません。
また、最近ではオンライン予備校や映像授業を併用できる通信制高校も増えており、自宅学習でも大学受験の準備ができる体制が整ってきています。必要なのは、「通信制だから無理」と決めつけない姿勢と、適切なサポートを活用する意識です。
専門学校進学の流れと通信制高校のメリット
専門学校への進学も、通信制高校からの進路として一般的な選択肢です。調理師、保育士、看護師、ITエンジニア、美容師など、実践的なスキルを身につけたい生徒にとっては専門学校が非常に魅力的な進路になります。
出願に必要な条件は「高等学校卒業(見込み)資格」であり、通信制高校の卒業生も同様に満たしています。さらに、面接や作文、実技試験で合否を判断するケースが多いため、学力試験に自信がなくても挑戦しやすいという特徴もあります。
通信制高校で自由な時間が多く確保できる生徒は、進学先の分野に関連したボランティアやアルバイト、資格取得に取り組むことができます。これが専門学校での面接や志望動機作成で大きなアピールポイントになるのです。
志望校合格につなげる3つの対策
通信制高校からの志望校へ合格するには、計画的な準備と情報収集が欠かせません。特に重要なのは、次の3つのポイントです。
- 進学目標を明確にする
- 受験に必要な学力や試験形式を早めに把握する
- 学校や外部のサポートを積極的に活用する
まず1つ目の進学目標を明確にすることは、なんとなく大学に行くという曖昧な動機では途中でモチベーションを失いやすくなります。行きたい学部や興味のある学問分野をしっかり考え、自分の将来像と結びつけておくことが大切です。
2つ目、受験に必要な学力や試験形式を早めに把握することですが、AO入試を考えるなら提出書類や面接対策を重視すべきですし、一般入試なら教科ごとの勉強計画を立てる必要があります。自分に合った受験方法を知ることが合格への近道です。
そして3つ目、学校や外部のサポートを積極的に活用することは担任や進路指導の先生、外部の予備校など、相談できる環境を作ることで不安を減らし、学習の方向性が明確になります。



通信制高校だからといって進学が不利になるわけではありません。必要な準備を早めに始めることが、希望の進路を実現する第一歩です。
このQ&Aで解決できなかった場合
今回のQ&Aについて「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。
ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。
いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。
※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。
※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。
通信制高校からの就職|難しいと思われる理由と現実
通信制高校に通う生徒や保護者の中には、「このまま卒業して就職できるのか」と不安を感じる人も多いでしょう。確かに、通信制高校は進学に強いというイメージが先行し、就職には向いていないと思われがちです。
しかし、就職実績や職種の傾向を見ていくと、通信制でも十分に就職は可能であることがわかります。
この章では、その誤解と実情、そして希望する仕事に就くために必要な準備や心構えについて詳しく解説します。
通信制高校はなぜ「就職に不利」と言われるのか
通信制高校は就職に不利とされがちですが、そこにはいくつかの誤解があります。特に、全日制に比べて登校日数や授業時間が少ないことから、「学力が不十分」「集団行動が苦手」といった偏見が根強く残っています。これは通信制高校に対する古いイメージが影響している部分もあります。
また、通信制高校の生徒は、進路相談や面接指導の機会が少ないと思われがちです。そのため、就職活動に関する情報や経験が不足しており、サポート体制が不十分と誤解されやすいのです。
さらに、就職先の企業によっては、通信制高校の履歴に対して不安を抱く担当者がいることも事実です。ただし、それはあくまで表面的な判断であり、面接時にしっかりと自分の強みや努力を伝えられれば、評価は大きく変わります。つまり、就職がうまくいくかどうかは、どんな学校に通っていたかよりも、どんな準備をして、どう行動したかが大きく影響します。
通信制からの就職実績と職種の傾向
通信制高校を卒業して就職する生徒は毎年一定数います。文部科学省の調査によれば、通信制高校の卒業生の約2割(23.1%)が卒業後すぐに就職の道を選んでおり、この割合は決して少なくありません 。(出典:文部科学省「高等学校通信教育の現状について」)
就職先としては、一般的に事務職や接客・販売業、例えばコンビニやアパレルなどの職種が多く見られます。そのほか、製造業や物流関係、介護や福祉関連の仕事、ITサポートや軽作業なども就職先として人気があります。就職先としては、一般的に事務職や接客・販売業、例えばコンビニやアパレルなどの職種が多く見られます。そのほか、製造業や物流関係、介護や福祉関連の仕事、ITサポートや軽作業なども就職先として人気があります。これらの職場では、学歴よりも人柄や仕事に対する意欲、そして継続して取り組む力が重視される傾向があります。
これらの職場では、学歴よりも人柄や仕事に対する意欲、そして継続して取り組む力が重視される傾向があります。
通信制高校に通いながらアルバイトを経験している生徒は、実際の社会経験や責任感を企業にアピールしやすく、評価されることも多いです。加えて、学校によっては就職を専門に支援する体制が整っており、求人紹介や面接練習、履歴書の書き方指導など、きめ細やかなサポートを受けられます。
こうした支援を上手に活用すれば、通信制高校に通っていても安心して安定した就職先を見つけることは十分可能です。進路に不安を感じる場合でも、しっかりと準備を重ねることで未来を切り開けます。
就職率を高めるために必要な3つの準備
通信制高校から希望する仕事に就くためには、ただ卒業するだけでは不十分です。早い段階からの準備がカギとなります。ここでは特に重要な3つの準備を紹介します。
- 高校在学中に社会経験を積む
- 履歴書や面接で伝える力をつける
- 進路指導や外部支援サービスを積極的に利用する
まず1つ目の高校在学中に社会経験を積むことですが、たとえばアルバイトやボランティアを通じて、働く現場の雰囲気やマナーを学ぶことができます。企業は履歴書の内容だけでなく、実際の行動から「働く力」を評価します。
次に履歴書や面接で伝える力をつけることですが、通信制高校では学び方や時間の使い方が個別なので、自己管理能力や目的意識を持って生活することが求められます。これをうまく言葉で説明できれば、一般の高校生以上に魅力的な人材として映ることもあります。
3つ目の進路指導や外部支援サービスを積極的に利用することは、学校にキャリアアドバイザーがいる場合は定期的に相談し、ハローワークや若者向けの就職支援施設も活用すると、求人情報が豊富に得られます。一人で抱え込まず、周囲と協力して動くことが成功への近道です。



就職は決して簡単ではありませんが、準備を重ねれば可能性は大きく広がります。通信制高校だから不利だと思い込まず、自分にできることから少しずつ積み上げていく姿勢が大切です。
このQ&Aで解決できなかった場合
今回のQ&Aについて「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。
ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。
いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。
※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。
※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。
進路が決まらない…通信制高校生が抱えやすい不安と対策
通信制高校に通う生徒の多くが、「進路がなかなか決まらない」と悩んでいます。実際、文部科学省によると、通信制高校の卒業生のうち進路未定の生徒は全体の31.5%にのぼります(出典:文部科学省「検討を進めるための参考資料」)。学びのスタイルが自由な分、将来の選択肢も広くなり、自分に何が合っているのか見えにくくなるのが原因です。この章では、通信制高校生が感じやすい進路の不安と、その解消法について紹介します。
よくある進路の悩みと原因とは
通信制高校に在籍していると、進路に関するさまざまな悩みが生まれます。中でも多いのが「進学か就職か決められない」「自分には何もできない気がする」「人より遅れている気がする」といった声です。
こうした不安の背景にはいくつかの要因があります。まず、通信制では進路指導や情報提供の機会が限られているため、自分から積極的に動かないと情報が手に入りにくいという現状があります。その結果、選択肢の幅が見えづらくなってしまいます。
また、個別に学習するスタイルが多いことから、自分の得意なことや興味のある分野に気づきにくいという面もあります。「何をしたいのか」「どんな仕事が向いているのか」がわからないまま不安を抱えるケースが目立ちます。
さらに、同年代の友人が進学や就職を順調に進めている姿を見て、「自分だけが遅れているのでは」と感じてしまい、焦りにつながることも少なくありません。
特に通信制高校では、日常的に進路の話をする機会が少ないため、自分の考えを言葉にすることが難しくなりがちです。さらに、学校生活に制限のある人や中退経験のある人は、将来への自信を失いやすい傾向も見られます。
しかし、こうした不安を感じるのは決して特別なことではありません。むしろ、しっかり悩んでいるということは、将来に向けて真剣に向き合っている証でもあります。大切なのは、悩みを放置せずに一つずつ整理していくことです。
自分に合う進路の見つけ方
自分に合った進路を見つけるには、「何が好きか」や「どんな生活を送りたいか」という視点から考えることが効果的です。自分の興味や価値観に基づいて選んだ進路は、モチベーションを保ちやすく、将来的な満足度にもつながりやすいからです。
一方で、学力や偏差値だけを基準に進路を決めてしまうと、自分に合わない環境に進んでしまい、入学後や就職後に後悔する可能性もあります。
まず、自分のこれまでの経験を振り返ってみましょう。楽しかったことや時間を忘れて集中できたことにヒントが隠れています。たとえば、「イラストを描くのが好きだった」「人に教えると喜ばれた」など、日常の中にある感覚が進路の方向性を教えてくれる材料になります。
また、「自分は何が得意なのか分からない」と感じる人は、周囲の人に聞いてみるのも一つの方法です。第三者の視点は、本人が気づいていない強みに気づく手助けになります。
進路を探すときに大切なのは、完璧な答えを一発で見つけようとしないことです。小さな興味をもとに選択肢を広げていく姿勢が、結果的に納得できる進路選びにつながります。
進路選びに迷ったときに活用できるサポート
進路に迷ったとき、ひとりで悩み続けるのではなく、誰かに相談することがとても大切です。通信制高校でも、進路指導の先生や担任の先生に相談することができます。普段あまり話す機会がなくても、思い切って声をかければ、しっかり時間を取って話を聞いてくれることが多く、頼れる存在です。
相談先は学校の中だけではありません。地域のハローワークでは「若者サポートステーション」という支援機関を通じて、進路についての相談や各種セミナーが用意されています。自治体が運営するキャリア支援窓口や、通信制高校と連携している進学・就職支援センターなども、利用価値の高い場所です。
こうした支援機関では、志望理由の整理や模擬面接、履歴書の書き方など、実践的なサポートが受けられる点が魅力です。何から始めればいいかわからないときでも、順を追ってアドバイスしてもらえるため、初めての就職活動や進学準備に心強い味方となってくれます。
また、インターネットを活用する方法も効果的です。進路情報サイトでは、大学や専門学校の情報に加えて、職業ごとの仕事内容や必要な資格なども知ることができます。通信制高校専門の情報サイトでは、実際に通信制で学んだ卒業生の体験談が多く紹介されており、進路決定のヒントを得ることができます。
情報を集め、誰かと話すことによって、自分の進みたい道が少しずつ明確になっていきます。不安を抱えたまま時間を過ごすよりも、行動に移すことで気持ちが楽になることもあります。身近なところから一歩ずつ踏み出してみましょう。



迷っている時こそ、行動することが状況を変える一歩です。サポートを使うことは「弱さ」ではなく、より良い未来をつかむための前向きな選択だと考えるようにしましょう。
このQ&Aで解決できなかった場合
今回のQ&Aについて「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。
ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。
いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。
※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。
※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。
通信制高校の進路サポート体制|学校選びが重要な理由
通信制高校では、自由な学習スタイルが選べる反面、進路指導の充実度に差があるのも事実です。進学や就職を考える上で、どのような支援を受けられるかは学校選びの大切なポイントになります。この章では、進路サポートが充実している通信制高校の特徴と、選ぶ際に確認しておくべきポイントを紹介します。
進学や就職に強い通信制高校の特徴
進路に強い通信制高校は、いくつかの共通した特徴を持っています。まず、進学や就職に関する専門コースやサポート制度が明確に整備されていることが挙げられます。たとえば、大学進学を目指す生徒向けに、推薦入試対策や小論文講座などを実施している学校があります。
また、就職を希望する生徒に対しても、ビジネスマナー講座やインターンシップの紹介など、実践的な支援が用意されているケースが見られます。企業とのパイプを持っている学校では、卒業生の紹介を通じた就職実績が豊富なのも特徴です。
さらに、生徒ひとり一人に合わせた個別の進路指導が受けられることも大切なポイントです。集団指導ではなく、面談を通じて個別の目標や状況を考慮したアドバイスを受けられる環境があると、納得のいく進路選びにつながります。
担任やカウンセラーによる支援内容
通信制高校でも、進路に関する支援を行う担任や専門のカウンセラーがいます。特にサポート体制が整った学校では、定期的な面談やキャリアカウンセリングが実施されており、早い段階から進路についての相談が可能です。
担任の先生は、学習状況の把握だけでなく、進学・就職を含めた生活全般の相談窓口となる存在です。カウンセラーは、生徒の心理的な不安や迷いに寄り添いながら、どの選択肢が適しているか一緒に考えてくれます。
たとえば、進学を目指す場合には、受験校の選び方や志望理由の整理、小論文の添削など具体的なサポートが受けられます。就職希望の生徒には、履歴書の書き方から模擬面接まで、実践的な指導が行われることも少なくありません。
これらのサポートを継続的に受けることで、生徒は自分の強みを理解し、希望する進路へ向かって自信を持って準備ができるようになります。単に「話を聞いてもらう」だけでなく、「次の行動につながる支援」があるかどうかが大切です。
自分に合った進路サポート校の見極め方
通信制高校を選ぶときは、カリキュラムや学費の比較だけでなく、進路サポートの充実度にも注目することが大切です。特に将来の進学や就職を見据えるなら、どれだけ個別に対応してもらえるかが重要な判断材料になります。
そのためには、パンフレットや公式サイトだけの情報では不十分です。実際に学校説明会やオープンキャンパスに足を運び、自分の目で確かめることが効果的です。現場の雰囲気や担当者の対応から、サポート体制の「リアルな姿」が見えてきます。
説明会では、過去3年間の進学・就職実績など、具体的なデータが公表されているかを確認してみてください。こうした実績を詳しく開示している学校は、進路支援に自信を持って取り組んでいるケースが多いです。
また、進路指導の担当者の専門性や相談のしやすさ、進路相談の頻度、模擬面接や書類添削などのサポート体制、さらに卒業後の進路フォローの有無も、見逃せないポイントです。これらの点をスタッフに質問することで、表には見えにくい支援の質を見極められます。
最も大切なのは、自分が不安を感じたときに、どれだけ親身に寄り添ってくれる環境があるかという点です。どんなに制度が整っていても、相談しづらい雰囲気では活用できません。実際に訪問した際の対応や雰囲気から、「ここなら安心して進路のことを話せる」と思える学校を選ぶことが、納得できる進路決定につながります。



サポート体制は目に見えにくい部分ですが、将来の進路に大きく影響します。学校選びの段階で慎重に比較し、自分の目で確かめることが後悔しない選択につながります。
このQ&Aで解決できなかった場合
今回のQ&Aについて「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。
ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。
いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。
※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。
※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。
通信制高校でも後悔しない進路を選ぶために必要な3つの対策
通信制高校に通っていても、自分に合った進路を選べば将来の可能性は大きく広がります。とはいえ、「進学して後悔したくない」「就職して失敗したらどうしよう」と不安を感じる人も少なくありません。ここでは、そんな後悔を防ぐために今から実践できる3つの対策を紹介します。
対策① 目標を明確にする
進路選びで最も大切なのは、自分がどんな未来を描きたいかを明確にすることです。「なんとなく進学」「とりあえず就職」では、入学後や入社後にミスマッチを感じやすくなります。
まずは、自分がどんなことに興味を持っているのかを考えてみましょう。好きなこと、得意なこと、大切にしたい価値観などをノートに書き出すだけでも、思考が整理されていきます。やりたい仕事が決まっていなくても、「どんな暮らしをしたいか」を考えることがヒントになります。
また、目標は一度決めたら終わりではありません。少しずつ見直して、成長とともに変化していくものです。曖昧な状態のまま進路を選ぶよりも、少しでも「こうなりたい」と思える方向性があることで、学びの意欲や行動にもつながります。
対策② 資格・スキルを身につける
将来の選択肢を広げたいと考えるなら、資格やスキルを身につけておくことが大きな武器になります。通信制高校に通う生徒は、登校日数や学習スケジュールに余裕がある分、時間を上手に使えばスキルアップのための学習に集中しやすいという利点があります。
たとえば、高校在学中でも取得しやすい資格には、MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)や簿記検定、ITパスポート、英検・TOEICなどの語学系、そして福祉に興味がある人には介護職員初任者研修などがあります。これらの資格は、進学や就職の場で自分の強みを示す材料として活用できる点が大きなメリットです。
「特別な才能がない」と不安を抱えている場合でも、身近な資格から少しずつ実績を積んでいけば、それが自信へとつながっていきます。さらに、プログラミングや動画編集、イラスト制作など、趣味をきっかけに学べるスキルも将来の仕事に結びつくことがあります。
興味のある分野から少しずつ手を伸ばし、自分なりの得意分野を見つけていくことが、将来の選択肢を広げる第一歩になります。
対策③ 情報収集と相談を怠らない
後悔しない進路選びをするには、早めに情報を集めることと、信頼できる人に相談することが欠かせません。通信制高校は登校日数が限られているため、進路について誰かと話す機会が少なくなりがちです。そのため、積極的に情報に触れ、自らサポートを求めていく姿勢が重要になります。
情報収集の方法としては、学校が開催する進路ガイダンスやオープンキャンパスへの参加が効果的です。インターネットでの進学先や求人情報の検索も役立ちますし、卒業生の体験談に目を通すことで、より現実的な視点が得られます。また、自治体のキャリア支援センターに足を運ぶのも、選択肢を広げるきっかけになります。
さらに、担任の先生やカウンセラー、保護者に迷っていることを素直に伝えることも大切です。たとえば、「この先どうすればいいかわからない」と話すだけでも、意外なアドバイスがもらえることがあります。言葉にして誰かに伝えることで、自分の考えが整理され、次の行動へとつながっていくはずです。



「こんなこと相談していいのかな」と思う内容でも、ためらわずに話してみることが第一歩です。情報は待っていてもやってきません。自分から取りに行く姿勢が、後悔しない選択につながっていきます。
このQ&Aで解決できなかった場合
今回のQ&Aについて「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。
ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。
いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。
※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。
※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。
後悔しない通信制高校の選び方│プロ直伝
自分に合った学校を選びやすい通信制高校ですが、残念ながら、「入学したけど、やっぱり合わなかった…」というケースが少なくないのが現状です。
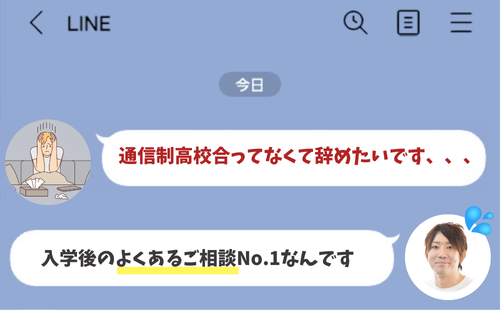
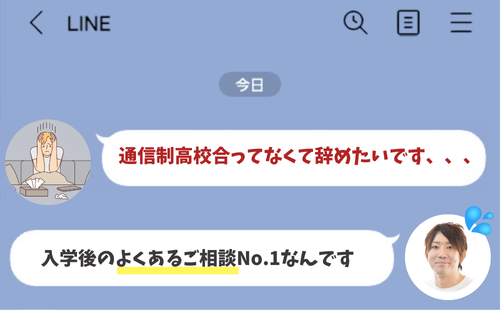
よくある原因として、
- 1つの学校しか検討しなかった
- 親の意向で決めてしまった
- 学校見学にも行かなかった
といったことが原因としてあげられます。
こういった後悔の声に共通しているのは、十分な比較検討をしなかったということです。この失敗を避けるには、複数の通信制高校を比較し、自分に合った学校を慎重に選ぶことが大切です。
そんな時に役立つのが、通信制高校の一括資料請求サービスです。住所を入力するだけで、通学圏内の学校のパンフレットを簡単に取り寄せられます。
各校の特徴や違いを把握しやすくなり、自分に合った学校を見つけやすくなりますよ。パンフレットは視覚的にも検討しやすく、「この学校は違うな」という見極めもしやすくなります。
まだ学校選びに迷っている方は、こうした資料請求サービスを活用してくださいね。
まずは多くの学校から検討していくことが大事なのですが、その話の進め方によっては、学習意欲の低下や中退につながってしまうケースもあります。
特に不登校経験がある場合は、本人の心の準備が整っているかどうかをしっかりと見極めることが大切です。進路の話を急かすのではなく、まずは日常的な会話から始めて、少しずつ本人の気持ちに寄り添っていきましょう。
もし進路の話ができないときは、当サイト管理人が運営する無料講座を受けてください。
関連:失敗しない進路の話の進め方3ステップ講座プレゼント中(不登校解決講座)
決して親の期待や周囲の意見だけで決めるのではなく、「なぜ通信制高校で学びたいのか」「どんな高校生活を送りたいのか」という本人の思いを丁寧に確認していくことが重要です。学校見学や体験授業にも参加して、実際の雰囲気を感じることで、より具体的なイメージが持てるはずです。
学校選びでは、サポート体制や通学のしやすさ、費用面なども含めて総合的に検討することが必要です。焦らずじっくりと情報を集め、本人と保護者が納得できる選択をすることで、充実した高校生活への第一歩を踏み出すことができるでしょう。
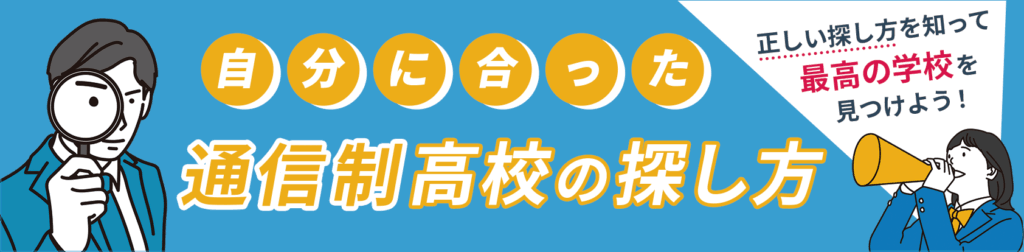
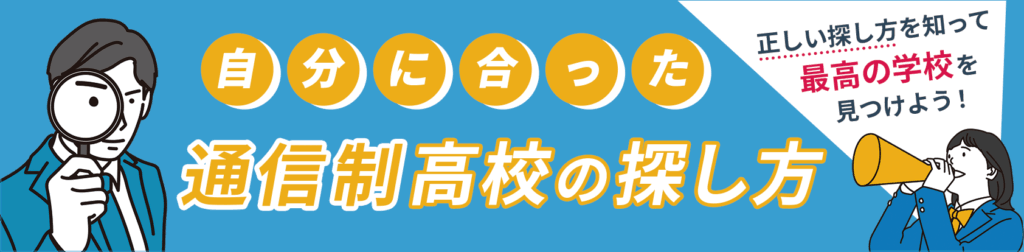
自分に合った通信制高校を探している方へ
通信制高校に入学したい、お子さんを通わせたいと思っても、どんな通信制高校があるのか探して、学校がご自身に合っているのか選ぶのは難しいものですよね。
高卒資格取得はもちろん、スクーリング日数やスクーリング形式、ご自宅からの通学のしやすさ、不登校からの学び直し、大学進学など、入学目的もさまざまですが、一番大切なのはその学校の雰囲気や環境がお子さん自身に合っているかどうかが大事です。
「通信制高校カフェ」では、〇〇県から通える通信制高校やサポート校の情報を豊富に掲載しています。まずは気になる学校を複数ピックアップして、資料請求をしていきましょう。
資料が手元にあると、「この学校はいいな」「この学校は合っていないな」と取捨選択もしやすいですし、お子さんとの情報共有もしやすいです。
また並行して、気になる学校が出てきたらぜひ当サイトの口コミも確認してみましょう。
口コミの正しい活用方法を知ることで、学校選びの貴重な判断材料となります。
例えば口コミで確認した情報を元に、学校見学の時に「先生方のサポート体制について詳しく教えていただけますか?」「オンライン授業の具体的な進め方を教えてください」など、気になった点を質問してみましょう。これだけでも、より具体的な情報が得られますよね。
口コミは「こういう点をチェックしよう」という参考程度に考えて、実際に自分の目で確かめることが大切です。ネットの情報に振り回されるのではなく、その情報を「確認すべきポイント」として活用していくのがおすすめです。
ちなみに、全国展開している通信制高校の場合、キャンパスによって環境が異なることもあります。だからこそ、資料請求し口コミを調べた後は、気になるキャンパスの見学会には必ず参加することをおすすめします。
口コミは「参考程度」として位置づけ、実際の見学や様々な情報源と組み合わせることで、より良い学校選びができるでしょう。


まとめ:通信制高校でも進学・就職は十分可能
通信制高校に通っているからといって、進学や就職が不利になるとは限りません。大切なのは、自分の目標に合わせた行動を早めに始めることです。進路に不安を感じるのは誰でも同じですが、正しい情報をもとに準備を進めることで、不安は確実に小さくなります。
この記事では、進学や就職に向けて押さえておきたいポイントや、進路が決まらないときの対処法、サポート体制の見極め方などを紹介してきました。どれも、今日から取り組める内容ばかりです。
「通信制高校だから難しい」と決めつけず、「通信制高校だからこそできる選択肢がある」と前向きに考えることが、納得できる進路への第一歩です。情報を集め、自分と向き合い、必要な支援を活用しながら、理想の進路を見つけていきましょう。
このQ&Aで解決できなかった場合
今回のQ&Aについて「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。
ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。
いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。
※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。
※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。
失敗しない通信制高校選びのコツ
自分に合った学校を選びやすい通信制高校ですが、残念ながら、「入学したけど、やっぱり合わなかった…」というケースが少なくないのが現状です。
よくある原因として、
- 1つの学校しか検討しなかった
- 親の意向で決めてしまった
- 学校見学にも行かなかった
といったことが原因としてあげられます。
こういった後悔の声に共通しているのは、十分な比較検討をしなかったということです。この失敗を避けるには、複数の通信制高校を比較し、自分に合った学校を慎重に選ぶことが大切です。


そんな時に役立つのが、通信制高校の一括資料請求サービスです。住所を入力するだけで、通学圏内の学校のパンフレットを簡単に取り寄せられます。
各校の特徴や違いを把握しやすくなり、自分に合った学校を見つけやすくなりますよ。パンフレットは視覚的にも検討しやすく、「この学校は違うな」見極めがしやすくなります。
まだ学校選びに迷っている方は、こうした資料請求サービスを活用してくださいね。
\ 最高に合った通信制高校を見つけよう /
当サイトの学校情報の内容に記載ミスや古い情報又は、新規キャンパスの情報がある場合は、お手数ですが下記の情報提供フォームからご連絡いただけますと幸いです。
>>通信制高校・サポート校情報提供フォームはこちら
この記事で解決できなかった場合
最後までお読みいただきありがとうございました。
今回の記事を読んで「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。
ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。
いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。
※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。
※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。
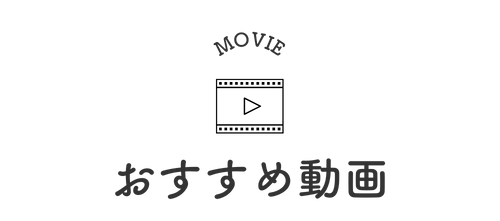
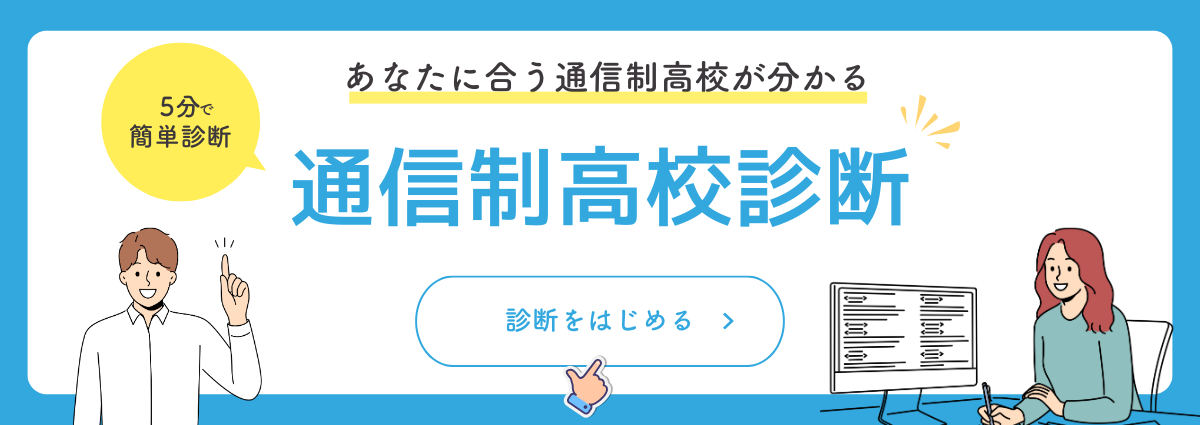
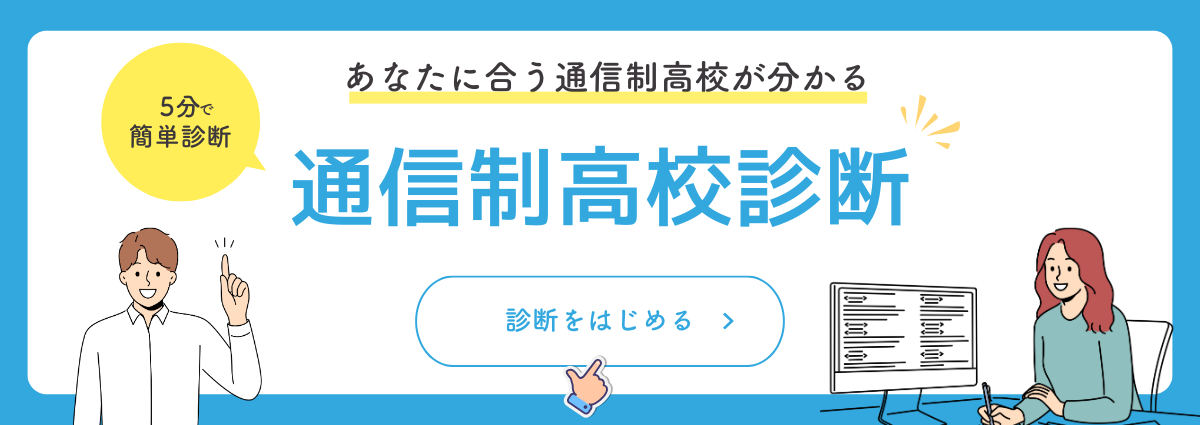


失敗しない通信制高校選びで大事なことは複数の通信制高校から検討することです。その最初のステップが資料請求です。
でも自分の地域から通える通信制高校を探すのは大変だし、1校1校入力フォームに資料請求していくのも大変です。更に資料請求しても音沙汰も無いことも…。



そんな情報収集に便利な一括資料請求サービスの利用がおすすめです。



無料で安心して利用できる以下のサービスを利用して効率的に情報収集していきましょう。
おすすめの資料請求手順
更に以下の「都道府県別!通信制高校・サポート校リンク」を利用して個別に資料請求すればあなたの地域から通える通信制高校の資料すべてを集めることができます! ➞ 全国から通える通信制高校(姉妹サイト)